2008-05-23[n年前へ]
■『理系サラリーマン 専門家11人に「経済学」を聞く! 』 
 「個性溢れる11人の経済学者の方々に話を聞く」という趣旨の本、『理系サラリーマン 専門家11人に「経済学」を聞く! 』が発売されました。大竹文雄・玄田有史・友野典男・松原隆一郎・小島寛之・奥村宏・西村和雄・森永卓郎・中島隆信・栗田啓子・中村達也という、11人の経済に関わる方々が、ものわかりの悪い生徒に実に丁寧に教えてくれたこと、その内容が本になりました。
「個性溢れる11人の経済学者の方々に話を聞く」という趣旨の本、『理系サラリーマン 専門家11人に「経済学」を聞く! 』が発売されました。大竹文雄・玄田有史・友野典男・松原隆一郎・小島寛之・奥村宏・西村和雄・森永卓郎・中島隆信・栗田啓子・中村達也という、11人の経済に関わる方々が、ものわかりの悪い生徒に実に丁寧に教えてくれたこと、その内容が本になりました。
本書には、一般の方々や経済学者の方々のアンケートから、「経済学者」「一般のひと」がそっくりだけれど、ほんの少しだけ違う姿が浮かび上がり、「豊かになるために必要なもの」をクラスタ分析した結果から、「希望とか自由とか愛」といった見えないものの繋がりを眺めたりすることができるオマケもついています。また、産業・科学や芸術・宗教といった歴史背景と、経済学の世界地図の上に時系列で並べた「歴史年表」もついています。
豊かになるために、小島先生はたくさんのものを選び、(「若い頃は時間があるけれど金がなかった。今は時間だけが必要…つまりは年をとったということです」といった言葉とともに)大竹先生と友野先生は時間だけを必要とし、森永先生は「愛」だけを選びました……
一般の方々や経済学者の方々へのアンケート結果、そこに記された言葉を眺めていると、不思議なほど私たち自身(そして私たちの分身のような経済学者の方々)の姿が見えてきます。そんな私たち自身の姿・私たち自身が望むことを眺めつつ、経済学者の先生方が話すこと読むのも、一興かと思います。
2008-05-24[n年前へ]
■続・『理系サラリーマン 専門家11人に「経済学」を聞く! 』 
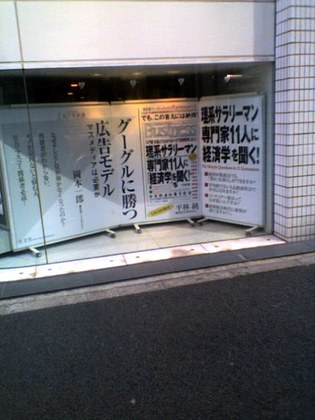 クールビズ・ウォームビズの効果に関するシミュレーション記事の「原稿料の分け方」を飲み屋で話したことをきっかけとして、『理系サラリーマン 専門家11人に「経済学」を聞く! 』は生まれました。
クールビズ・ウォームビズの効果に関するシミュレーション記事の「原稿料の分け方」を飲み屋で話したことをきっかけとして、『理系サラリーマン 専門家11人に「経済学」を聞く! 』は生まれました。
私が授業を受けた11人の経済学者の先生たちには、2つの特徴があったように思います。1つは、ものごとを色々な方向から眺め一種冷めた考え方もする、ということでした。そして、もう1つは、多くの人と同じように、先生方の仕事への熱意は「素朴で単純な」暖かな気持から生まれているのかもしれない、と感じたことです。つまり、クールな頭とウォームな心が混じりあっていた、ということです。
「はじめに」
単行本にするにあたり、コラム(今気づきましたが、p.217のフローチャート中の「上がる」「下がる」が逆になっていました)や読んで欲しいと感じた本の「ブックガイド」を書き足しました。インタビューから少し時間を経てから書いたものですが、その分、少し漬かっていて味が深まっていると良いな、と願っています。
何より大変で、なおかつ、何より一番新鮮だったのが「経済学者の先生方に行ったアンケートの集計作業」でした。「好きな経済学者とその理由」「分数もできないみんなの判断でも”正しい”ことが多いと思うか?」「豊かになるために必要なものは何ですか?」という3つの拙い設問に対して書かれた言葉は、本当にどれも新鮮に感じたのです。記事中で先生方が語った言葉をアンケートに書かれた言葉とともに読み直したい。改めてその言葉を聞き返したいと強く感じさせられました。
「経済学の目的はみんなを幸せに豊かにすること」だといいます。それならば、「幸せ・豊かさ」とは一体何なのでしょうか。そんな「豊かさ」というものは、人が自分自身で見つけ出すしかないのかもしれません。そんな「豊かさ」は少し「孤独」と似ています。
最終ページ 中村達也著「豊かさの孤独」に対する紹介文
2009-01-18[n年前へ]
■「相場師」のケインズ 
 「相場ヒーロー伝説 -ケインズから怪人伊東ハンニまで」から。
「相場ヒーロー伝説 -ケインズから怪人伊東ハンニまで」から。
「(ジョン・メイナード・ケインズ)彼が残した財産は総額四十五万ポンド。今なら二十億円を超す額だ。投機の決算は『大もうけ』だった」(中略)勝海舟が言っている。「経済のことは経済学者にはわからない。それは理屈一方から見るゆえだ。世の中はそう理屈通りいくものではない。人気というものがあって、何事も勢いだからね」(『氷川清話』)勝海舟は経済学者には経済はわからないと決め付けるが、どうして、どうしてケインズは「人気」も「勢い」もわかっていた。だからこそ投機という難事業に成功したのである。
お金というのは不思議なものです。・・・ほんのわずかな知識と、特別な経験の成果として、金は容易に(そして、文字通り不当にも)ころがり込んでくるものです。
ジョン・メイナード・ケインズ 「母にあてた手紙」
2009-03-03[n年前へ]
■「バブルは繰り返す」と「学者の態度」 
バブル崩壊以降の株価最安値更新だそうです。けれど、それは、なぜかずっと前からから見えていた確実に来る「未来」だったようにも思えます。
 少し前、とても曖昧な質問を経済学者の方々に投げかけたことがあります。(「理系サラリーマン 専門家11人に「経済学」を聞く!
少し前、とても曖昧な質問を経済学者の方々に投げかけたことがあります。(「理系サラリーマン 専門家11人に「経済学」を聞く!
」)
「分数もできない大学生」のような"みんな"が行う判断は正しいと思いますか?ここで、大事なのは、”みんな”には私も入っていれば、あなたも入っている。つまり、すべての人が入っているということです。そして、「コモン」といった言葉が踊る文章を見るたびに、少し不思議に浮かびあがる疑問を、上手く言葉にできないままに投げかけてしまった質問です。
「合理的で明晰な経済人ではないだろう現実の人たち、そんな"分数もできない大学生"のような"みんな"が日日選択を繰り返すことで動いていく社会、そんなみんなが動かす社会が決める需要・供給・価格といったものの調整は、本当にみんなが幸せ・満足するものなのでしょうか?」くらいには、限定した質問に変えておけば良かったかもしれない、とも思いましたが、とにかく最初は曖昧な質問を投げかけてしまったのです。
その結果、前述の実に曖昧で不完全な質問に対して投げ返された言葉を読むことになりました。これが、不思議なことに、とても「納得感」がありました。
たとえば、ある先生のこんな答、
「すべてを疑ってかかるのが学者の思考方法ですが、最初から間違っていると思っているわけでもありません。あんまり最初から決めつけるということそのものをしないので。この質問には答えられません」
 あるいは、他のある先生のこういった言葉、
あるいは、他のある先生のこういった言葉、
「分数ができても、みんなが正しい判断をするとは言えない。金融工学がいかに進もうと、バブルは繰り返す」という言葉、どの答も真摯かつ正確な答えに感じられたのです。たとえば、上の答えからは、真摯に「向き合う態度」が見えてきますし、下の言葉からは、今日、今現在の世界がそのまま映し出されているようにも思えます。
他にも、「理系サラリーマン 専門家11人に「経済学」を聞く!
」を本にする段階で投げたこの質問(設問)の他回答から、いくつも感じたことがあります。それはまた、いつか、言葉にしてみたいと思います。
2009-03-04[n年前へ]
■夜の灯台で繋がる日本列島の姿 
 優れた雑誌を20挙げてください、と言われた時、Graphication は必ずその20誌の中に入る。しかも、無料で送付してくれることも考えてみれば、実にありがたい雑誌である。Graphicationの最新号 2009 No.161 のテーマは、「連」、つまり連なる、ということである。下に引用した文章は、その最新号の冒頭に書かれた言葉である。紹介サイトに書かれている文と比べてみれば、さらに、この号を作らんとした熱意・作っていた際の気持ちが透けて見えてくる。
優れた雑誌を20挙げてください、と言われた時、Graphication は必ずその20誌の中に入る。しかも、無料で送付してくれることも考えてみれば、実にありがたい雑誌である。Graphicationの最新号 2009 No.161 のテーマは、「連」、つまり連なる、ということである。下に引用した文章は、その最新号の冒頭に書かれた言葉である。紹介サイトに書かれている文と比べてみれば、さらに、この号を作らんとした熱意・作っていた際の気持ちが透けて見えてくる。
人々が分断され、競争に駆り立てられ、揚句の果てにゴミのように切り捨てられる。そんな社会を誰が望んだであろうか。こんな国の施策を助長した経済学者の一人が懺悔の書を書いた。遅すぎる気もするが、いま求められているのは人と人のつながりであり、共に生きるための知恵だろう。
 同じGraphicationの号の中の話だが、日本中の「灯台」の写真とその解説の記事がある。海際にそそり立つ、日本各地の灯台の景色がとてもきれいだ。そこには、こんな文章がある。
同じGraphicationの号の中の話だが、日本中の「灯台」の写真とその解説の記事がある。海際にそそり立つ、日本各地の灯台の景色がとてもきれいだ。そこには、こんな文章がある。
灯台は日没で点灯し、夜明けと同時に消灯する。日本列島の夜の地図を頭に浮かべてみてほしい。日本で最も日没が速い最東端の納沙布岬灯台(北海道)から転倒し、リレー式に最西端の与那国島の西埼灯(沖縄県)に光が灯る頃、日本列島の輪郭が光のリングで結ばれる。これは、140年変わっていないし、永遠に変わらぬ光景だろう。
山崎 猛
 この詩的な言葉を読んでいると、「繋がっていた双生児」をめぐる物語、灯台に引き寄せられていくものたちを扱った、野田秀樹(萩尾望都 原作)の「半神
この詩的な言葉を読んでいると、「繋がっていた双生児」をめぐる物語、灯台に引き寄せられていくものたちを扱った、野田秀樹(萩尾望都 原作)の「半神あらゆる海、あらゆる時間、あらゆる霧の中を押し分けて、剥き出しのまま届きぼくのなかに響く声、…引き剥がすことのできない声を発する装置。(灯台が発する声である)「霧笛」だ。
萩尾望都・野田秀樹の戯曲「半神」には、「霧笛」のある一部分が引用されていて、交錯するこのふたつのテクストは、まるで「霧笛」のなかの灯台とそれに相対する怪物の声のように、それぞれぼくの霧の中で深い孤独のうちに呼応しあっている。
「半神」は孤独、決定的なひとつの不在を生きること、について描き、「霧笛」はその孤独な他者へ呼びかける声の乗り越えられなさを描いていると言っていいかもしれない。ともかくどちらも、深い愛についての話だ。


